この記事には、アフィリエイト広告が含まれています。
今回は家庭を持っているおじさんにとっては必ず通るであろう問題について、わたくし、おじさん流のスタイルを皆様に共有させていただきます。
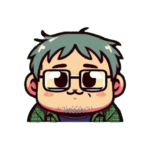 ボンおじ
ボンおじ耳の穴かっぽじいて聞いてくれよな!
はじめに


こんにちは。ボンおじです。
気がつけばアラフォーも後半戦、家族もあり、仕事の責任も重くなってきた今日この頃。
それでもゲームへの愛は変わらず、むしろ年々深まっているという同世代の皆さん、お疲れ様です。
今回は、我々アラフォー世代が直面する永遠のテーマについて語りたいと思います。


それは「仕事」「家庭」「ゲーム」という三つの大きな要素を、どうバランス良く両立させるかということ。
若い頃のように夜通しゲームをプレイするわけにもいかず、かといってゲームを完全に諦めるのも寂しい。
家族との時間も大切にしたいし、仕事でも結果を出さなければならない。
そんな複雑な状況の中で、現実的にゲームと付き合っていく方法を、実体験を交えながらお話ししていきます。
時間という最大の敵と向き合う


現実を受け入れる勇気
まず最初に受け入れなければならないのは、「時間は有限である」という厳しい現実です。
学生時代や独身時代のように、丸一日をゲームに費やすことはもうできません。
平日の夜は家族との時間があり、休日も家族サービスや家事、その他の用事で埋まってしまいがちです。
この現実を受け入れずに、昔と同じようにゲームをしようとすると、必ずどこかに歪みが生じます。
仕事でミスが増えたり、家族との関係がギクシャクしたり、睡眠不足で体調を崩したり。
そうなってしまっては元も子もありません。


「質」重視のゲーム選択
時間が限られているからこそ、ゲーム選びは慎重になる必要があります。
昔のように「話題になっているから」「安売りしているから」という理由で手当たり次第に購入するわけにはいきません。
私が重視しているのは以下のポイントです:
30分程度の短時間でも楽しめる、セーブがいつでもできる、中断・再開が容易など、細切れ時間でもプレイできるゲームを優先的に選ぶようになりました。
限られた時間とお金を投資するなら、長く楽しめるゲームを選びたいものです。
一度クリアしたら終わりではなく、繰り返しプレイできる要素があるかどうかも重要な判断基準です。
子どもがいる家庭なら、家族で一緒に楽しめるゲームも積極的に取り入れたいところです。
Nintendo Switchのパーティーゲームや協力プレイができるゲームは、家族の時間とゲーム時間を両立させる強い味方になります。
私の妻はほとんどゲームをプレイしないため、この項目からは除外されますが…。
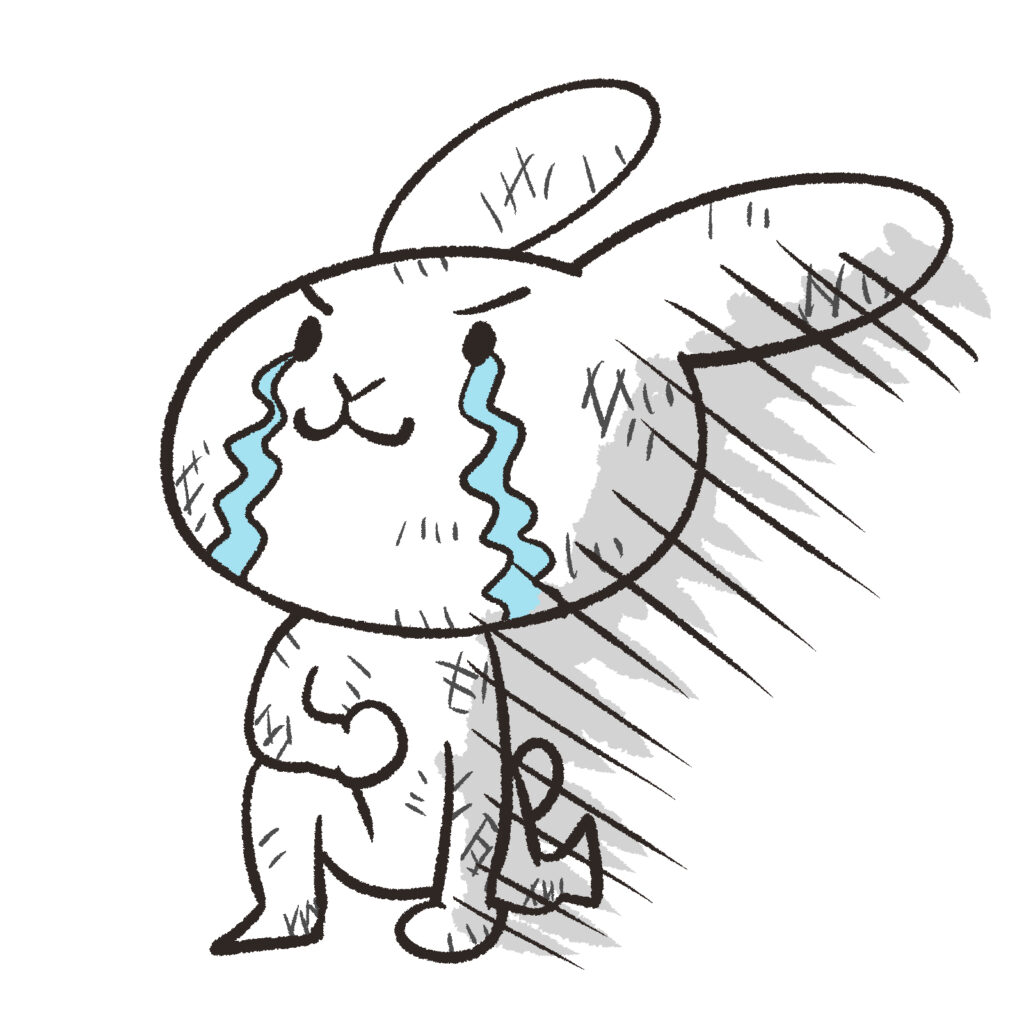
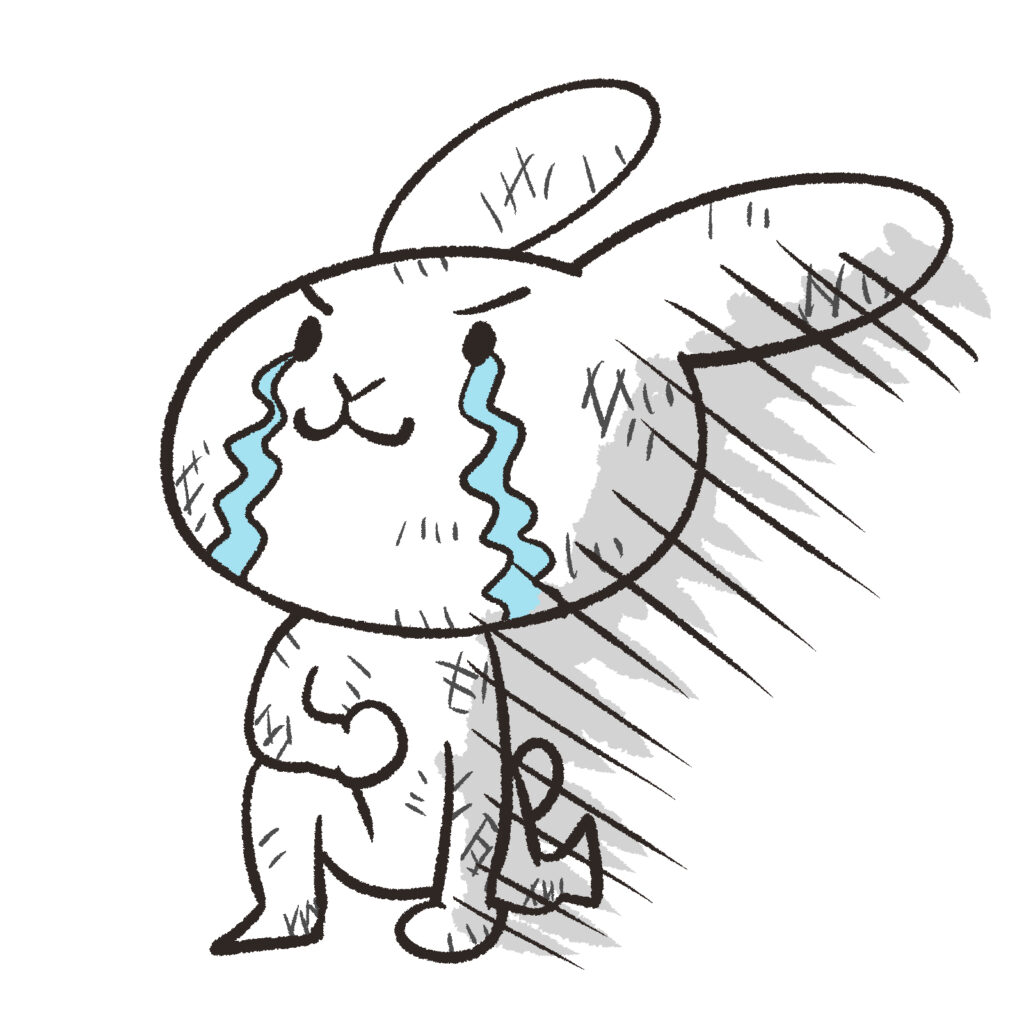
平日の限られた時間を最大活用する


「ながらゲーム」の活用術
平日にまとまった時間を確保するのは困難です。
そこで有効なのが「ながらゲーム」という考え方。
完全に集中してプレイするのではなく、他の作業と並行してできるゲームを活用するのです。
例えば、スマートフォンのパズルゲームを通勤電車で楽しんだり、家事の合間にターン制RPGを少しずつ進めたり。
最近ではリモートワーク方も増えてきたと思うので、休憩時間に短時間でプレイできるゲームもありかと思います。(リモートワーク羨ましい!!)
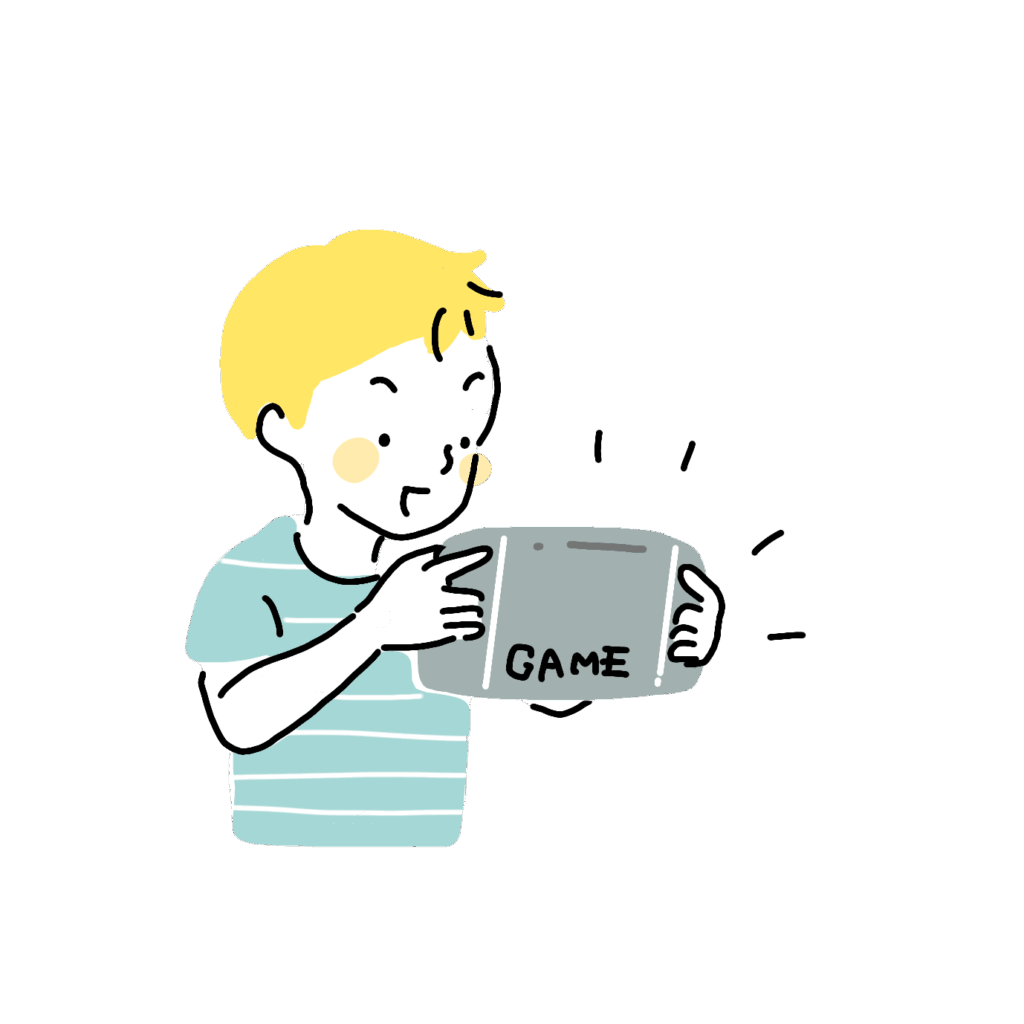
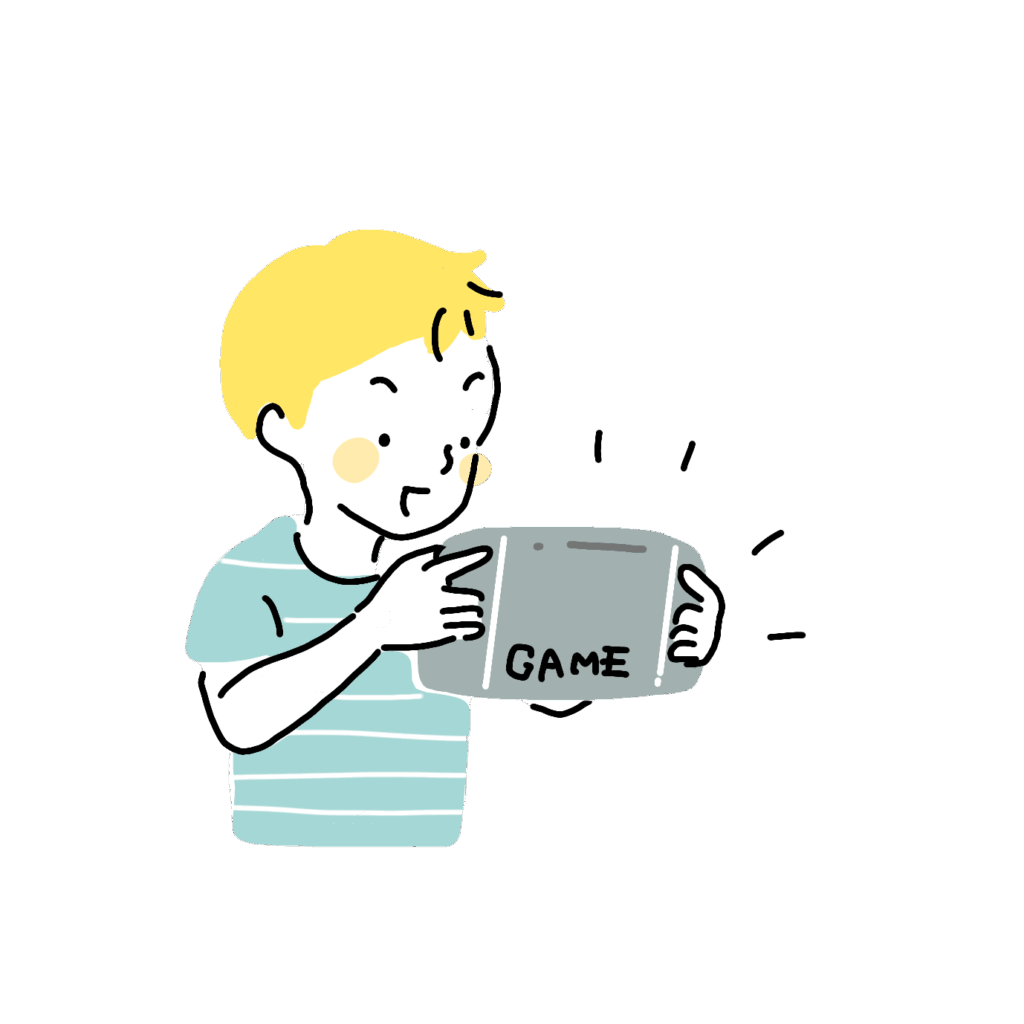
早朝ゲーム時間の確保
意外に穴場なのが早朝の時間帯です。
家族がまだ寝ている早朝に1時間程度早起きして、自分だけのゲーム時間を確保する方法です。
朝は頭がスッキリしているので、集中力が必要なゲームにも適しています。
アクションゲームの難しいボス戦や、戦略シミュレーションの複雑な局面などは、疲れた夜よりも朝の方がうまくいくことが多いです。
ただし、これは早寝とセットで考える必要があります。
夜更かしして朝も早起きでは、体調を崩してしまいます。


昼休みの有効活用
職場環境にもよりますが、昼休みの時間も貴重なゲーム時間として活用できます。
スマートフォンゲームはもちろん、Nintendo Switchのようなポータブル機なら、より本格的なゲームも楽しめます。
ただ、私はPCゲームのプレイがメインのため…、悲しいです…。
同僚にゲーム好きがいれば、一緒にプレイすることで職場でのコミュニケーションにもつながります。
最近では、職場でのeスポーツ大会を開催する企業も増えており、ゲームが新しい社内コミュニケーションツールとして注目されています。
休日の時間配分戦略
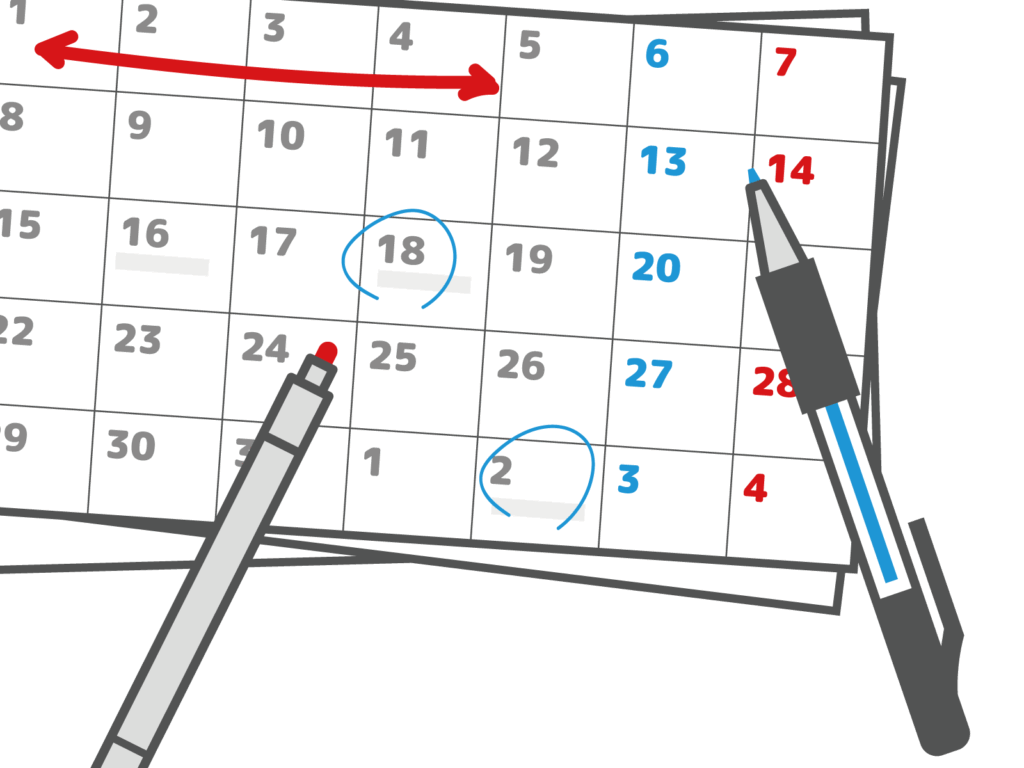
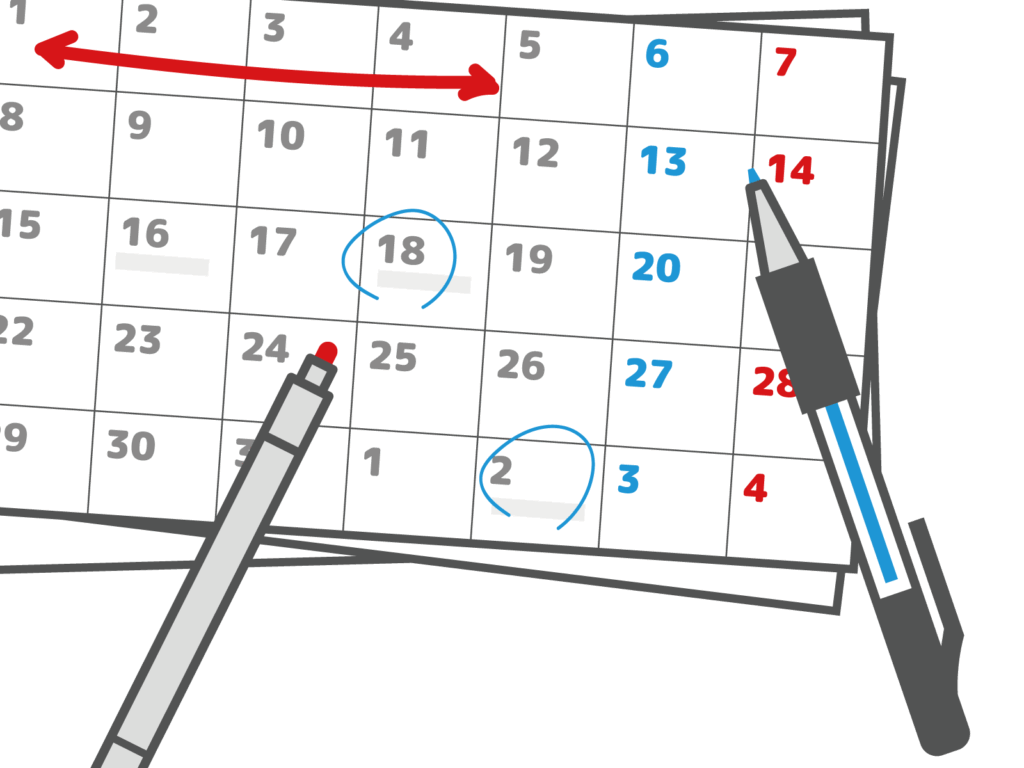
家族サービスとの両立
休日は家族との時間を大切にしつつ、自分のゲーム時間も確保したいところです。
ここで重要なのは、事前の計画と家族との相談です。
「今度の日曜日の午後2時間だけ、自分の時間ちょうだい!」というように、事前に相談しておくことで、家族も理解してくれやすくなります。
もちろん、その他の時間は家事をする前提ですよ!
サプライズで突然ゲームを始めるよりも、計画的にアプローチする方が円滑です。
メリハリのある時間の使い方
休日だからといって、だらだらとゲームをするのは効率的ではありません。だらだらやるゲームがいいんですけどね…。
「午前中は家族と過ごして、午後の2時間はゲーム、夕方からは家族の時間」というように、明確に時間を区切ることが大切です。
時間を区切ることで、家族に対しても「ちゃんと時間を決めてプレイしている」ということが伝わりますし、自分自身も集中してゲームを楽しむことができます。
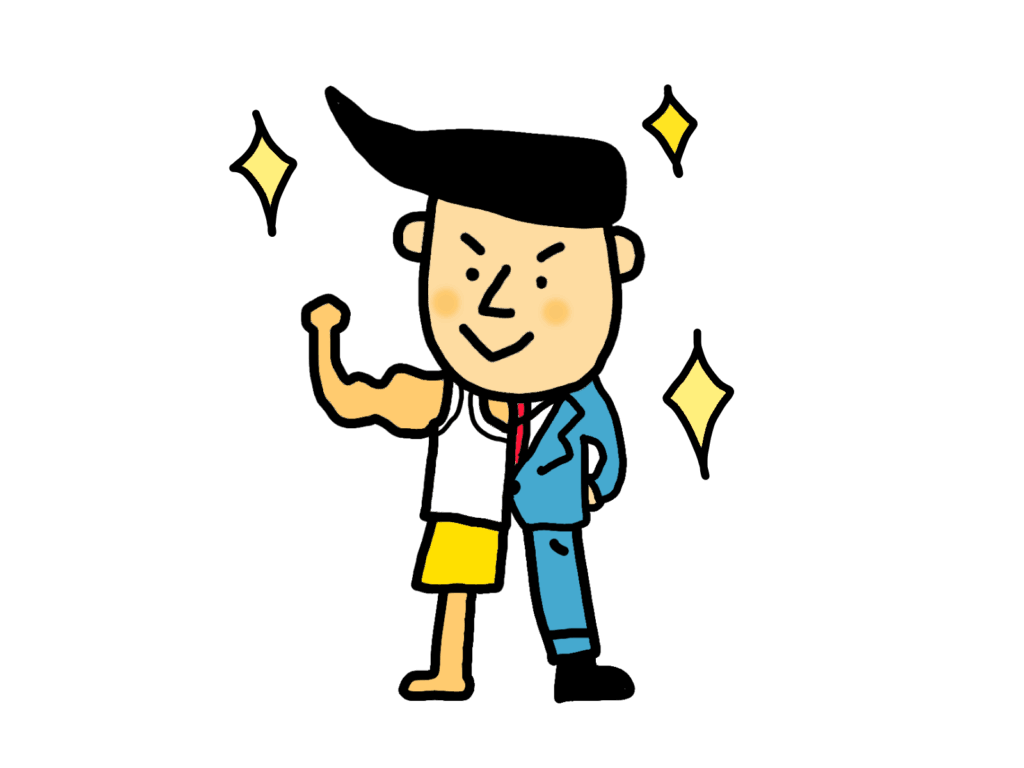
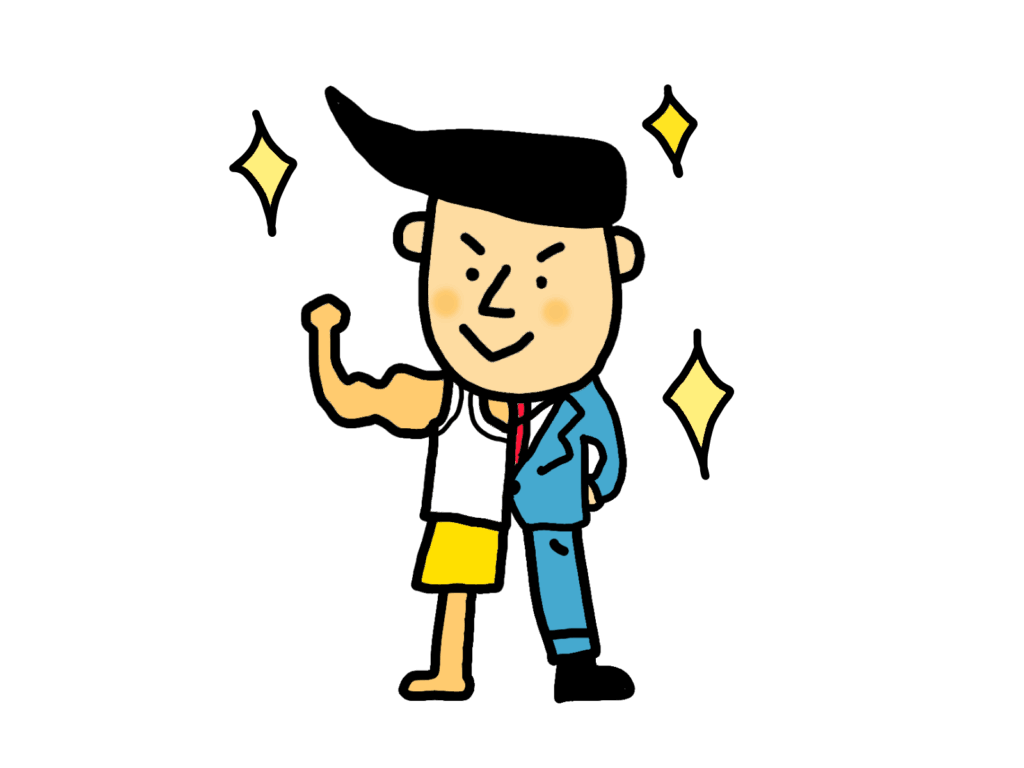
家族の理解を得るためのコミュニケーション
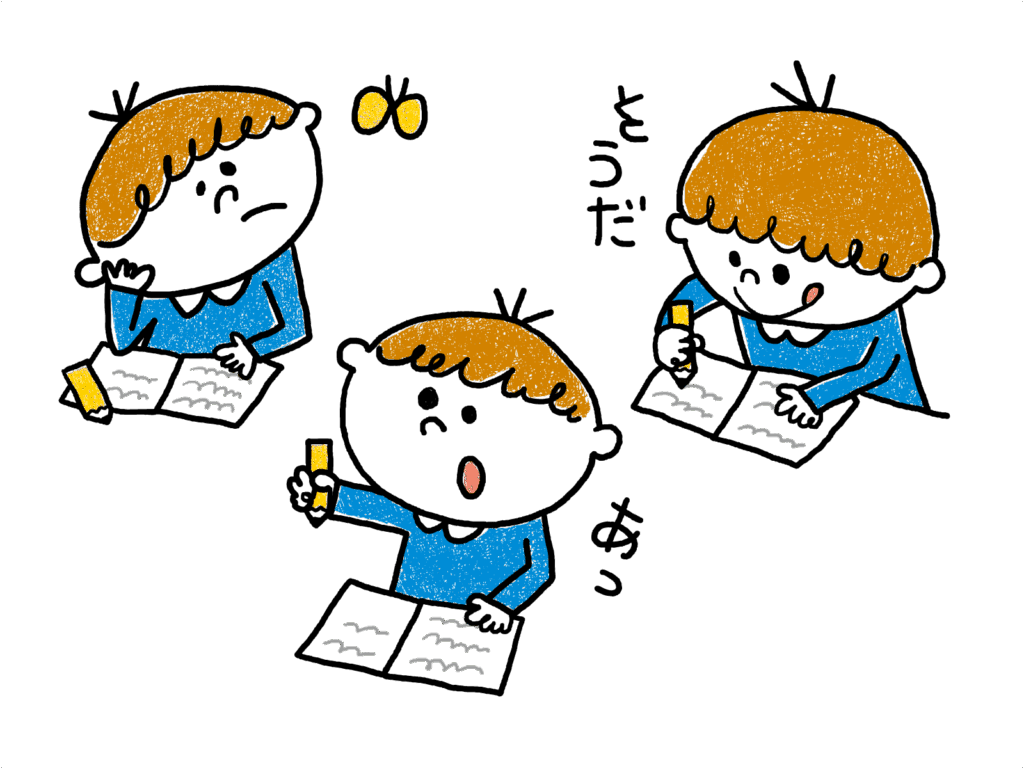
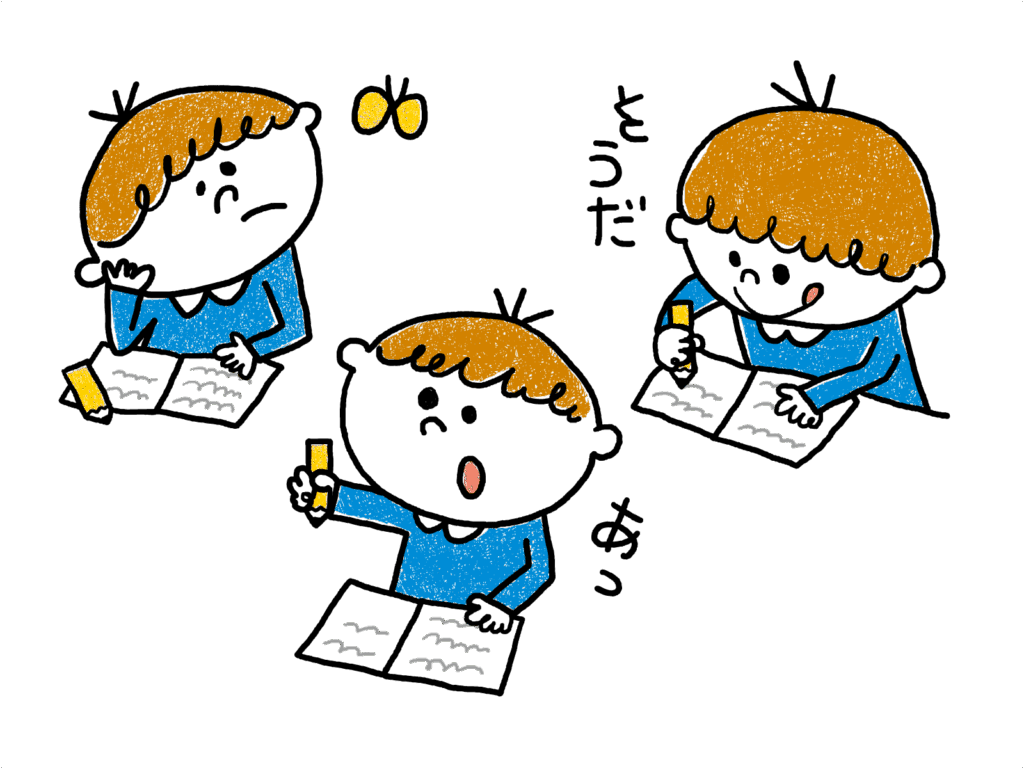
ゲームに対する偏見を解く
アラフォー世代の配偶者の中には、「ゲーム=子どもがするもの」「大人がゲームをするのは恥ずかしい」という固定観念を持っている人もいます。
そうした偏見を解くためには、ゲームの多様性や教育的側面、社会的な意義などを伝えることが効果的です。
「このゲームは歴史の勉強にもなるんだよ」「パズルゲームは認知症予防にも効果があるらしい」「オンラインで昔の友人とコミュニケーションが取れる」など、ゲームのポジティブな側面を具体的に説明することで、理解を得やすくなります。
家族も巻き込む戦略
可能であれば、家族もゲームに巻き込んでしまうのが最も効果的です。
一緒にプレイできるゲームを選んで、家族みんなで楽しむ時間を作る。そうすることで、ゲームが「家族の敵」ではなく「家族の娯楽」になります。
子どもがいる家庭なら、教育的なゲームを一緒にプレイしたり、親子でクリアを目指すゲームに挑戦したりするのも良いでしょう。
配偶者には、一緒に楽しめるパズルゲームやクイズゲームから始めて、徐々にゲームの楽しさを伝えていくという方法もあります。
うちは子どももいないため子供作戦は使えないし、妻を何度か巻き込もうとしましたが不発に終わりましたが…。(笑)


仕事とゲームの相乗効果を活用する


ゲームから学ぶビジネススキル
意外に思われるかもしれませんが、ゲームで培ったスキルが仕事に活かされることは少なくありません。
戦略シミュレーションゲームで身につけた計画性、RPGで学んだ目標設定とステップアップの考え方、アクションゲームで鍛えた瞬間的な判断力など、ゲームには仕事に応用できる要素がたくさんあります。
こうした視点でゲームを捉えることで、「仕事のためのスキルアップ」という大義名分も得られます。
実際に、ゲームを人材育成に活用する企業も増えており、ゲーミフィケーションという概念も注目されています。
ストレス発散としてのゲーム
仕事でのストレスを適切に発散することは、長期的な仕事のパフォーマンス向上につながります。
ゲームは手軽で効果的なストレス発散方法の一つです。
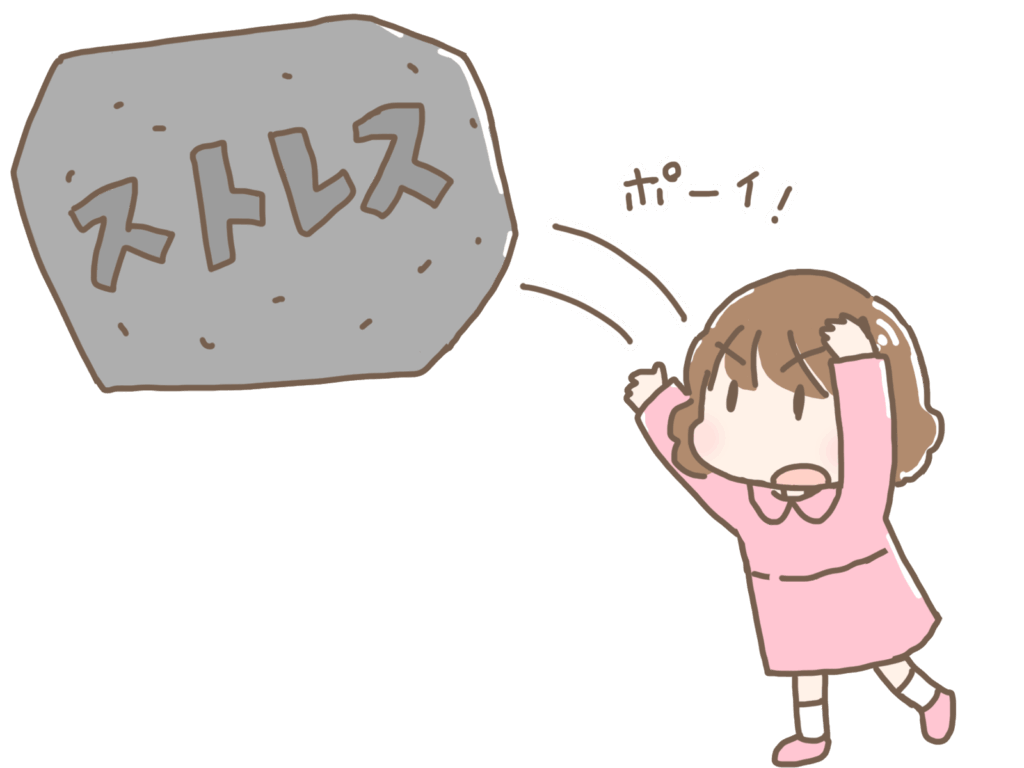
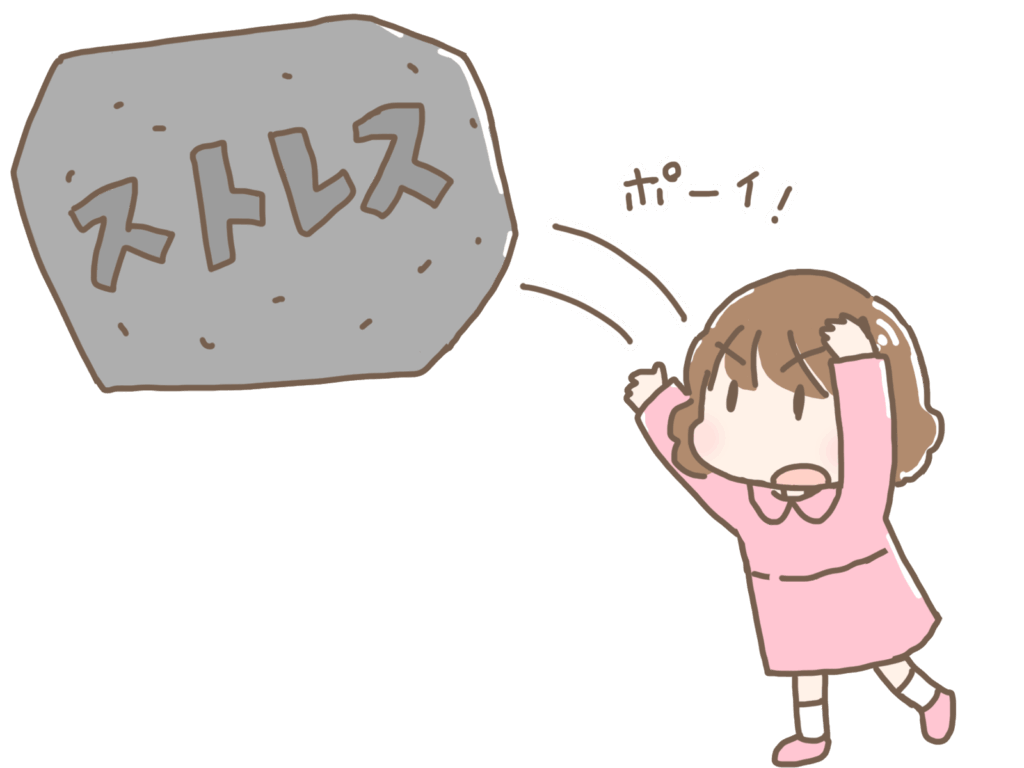
特に、現実では体験できない爽快感や達成感を味わえるゲームは、仕事の疲れを癒すのに最適です。
ただし、夜遅くまでプレイして翌日の仕事に支障をきたすようでは本末転倒です。適度な時間でプレイを切り上げる自制心も必要です。
健康管理との両立
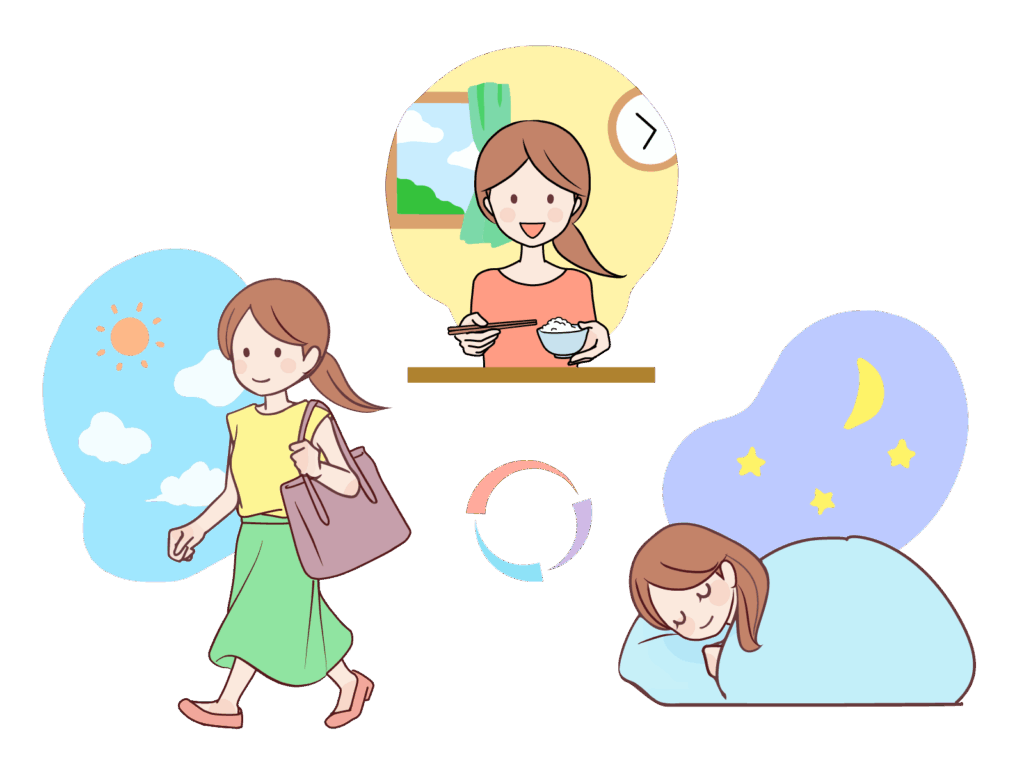
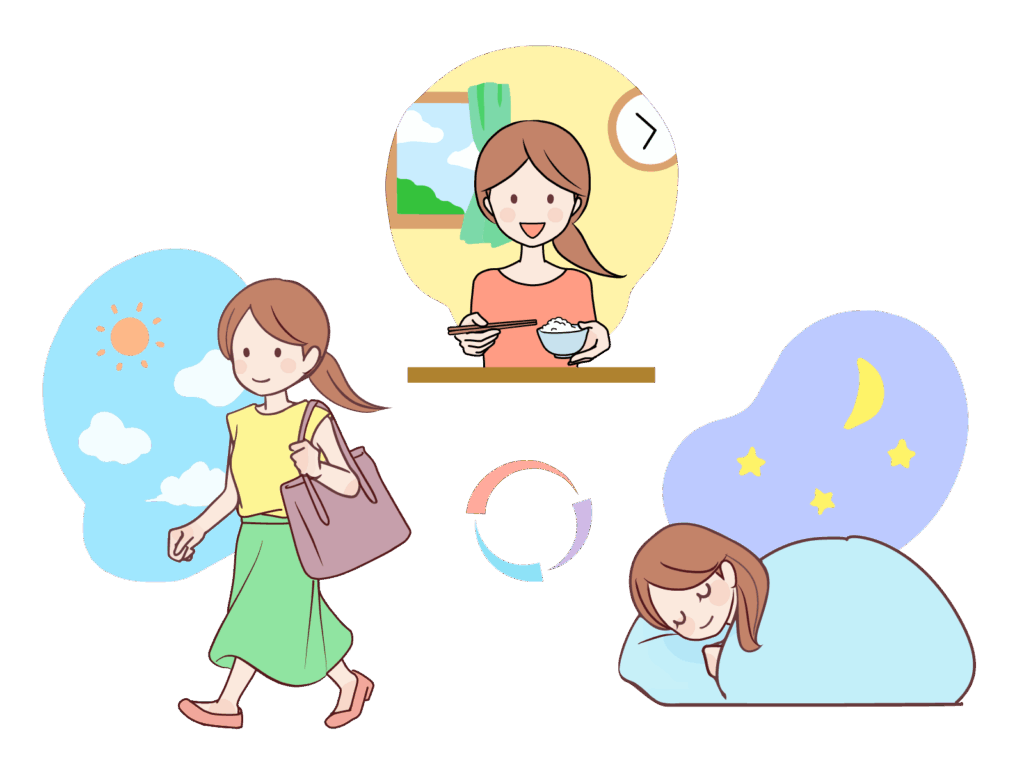
身体への配慮
アラフォーになると、体力の衰えや視力の低下、肩こりや腰痛など、様々な身体的な変化が現れます。
ゲームをプレイする際も、これらの健康面に配慮する必要があります。
定期的な休憩を取る、適切な姿勢でプレイする、画面との距離を保つ、部屋を明るくするなど、基本的な健康管理は欠かせません。
また、ブルーライトカット眼鏡の使用や、ゲーミングチェアの導入なども検討する価値があります。
運動との組み合わせ
最近では、体を動かしながら楽しめるゲームも増えています。Nintendo SwitchのRing Fit AdventureやFitness Boxingなどは、運動不足解消とゲームの楽しさを両立できる優れたタイトルです。
家族と一緒に体を動かせるゲームなら、健康管理と家族サービス、ゲームの楽しさを同時に満たすことができます。
お金稼ぎながら運動という手もあります!
それはポスティングです。


経済的な配慮とゲーム購入戦略
予算管理の重要性
アラフォー世代は、住宅ローンや子どもの教育費、将来の備えなど、様々な支出があります。
ゲーム代も家計の一部として、計画的に管理する必要があります。
月額でゲーム関連の予算を決めて、その範囲内でやりくりするのが基本です。
衝動買いを避けるために、欲しいゲームはリストアップしておいて、予算と相談しながら優先順位をつけて購入するようにしています。
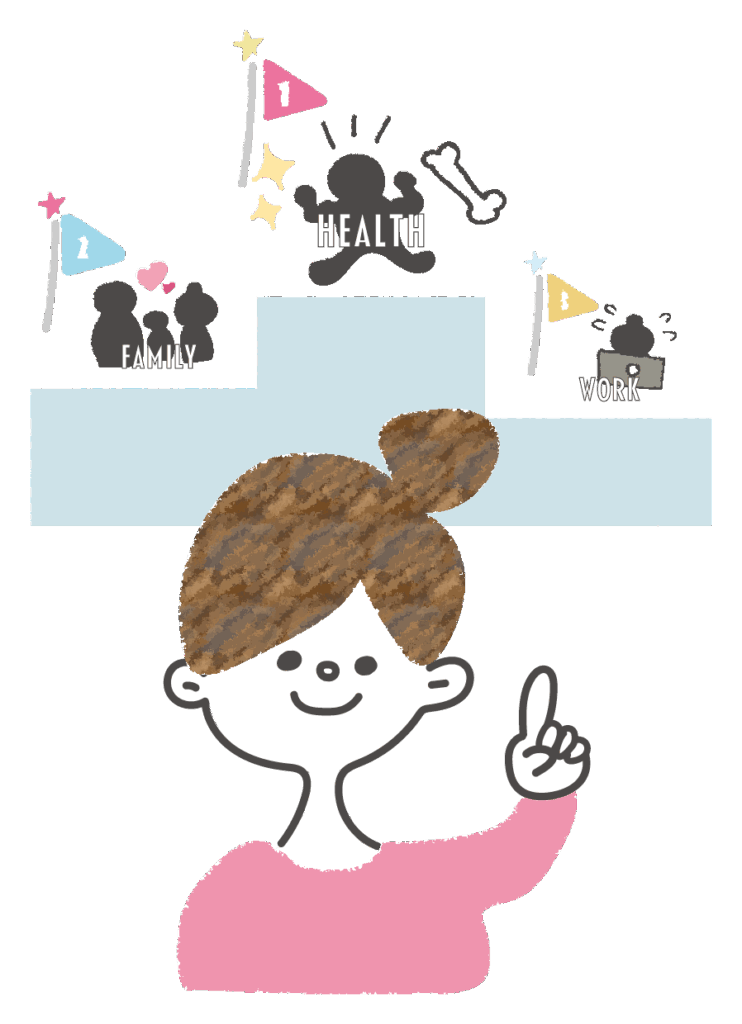
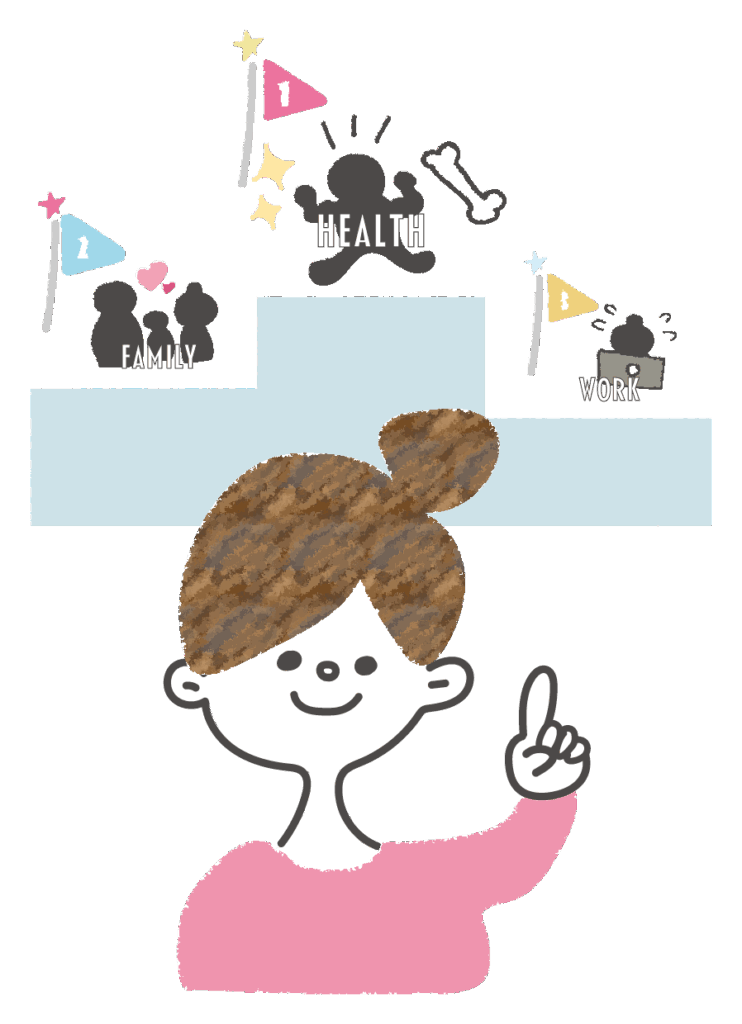
コストパフォーマンスを重視した選択
限られた予算の中でゲームを楽しむには、コストパフォーマンスを重視した選択が重要です。


サブスクリプションサービスの活用もその一つです。Xbox Game PassやPlayStation Plusなどは、月額料金で多数のゲームが楽しめるため、個別にゲームを購入するよりもお得になることが多いです。
また、発売から時間が経ったゲームのセール情報をチェックしたり、中古ゲームを活用したりすることで、予算を有効活用できます。
オンラインコミュニティとの付き合い方
同世代ゲーマーとのつながり
オンラインゲームやSNSを通じて、同世代のゲーマーとつながることも、ゲームライフを豊かにする要素の一つです。
アラフォーにもなると、友人と中々会うことが出来ず、家族と仕事の人間関係しかなくなりがちです。
私は何度かMinecraftをマルチでプレイする環境を整え、Xなどでメンバーを募り、皆で楽しくプレイした経験もあります。
同じような環境にいる人たちと情報交換したり、一緒にプレイしたりすることで、より深くゲームを楽しむことができます。
ただし、オンラインでの交流も時間を消費します。
リアルの人間関係に影響を与えない程度に、適度な距離を保つことが大切です。


情報収集の効率化
ゲーム関連の情報は日々大量に発信されています。
全てをチェックしようとすると時間がいくらあっても足りません。
自分の興味のあるジャンルやシリーズに絞って情報収集することで、効率的にゲーム選びができます。
YouTubeやTwitchでのゲーム実況を通勤時間に見たり、ゲーム雑誌の電子版を隙間時間に読んだりするのも効果的です。
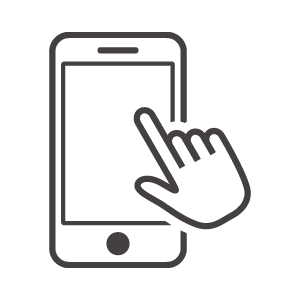
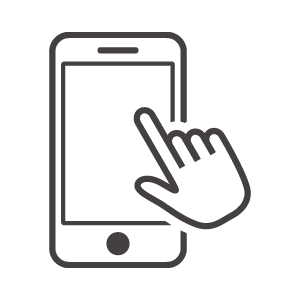
将来を見据えたゲームライフ
長期的な視点での楽しみ方
アラフォーの今だけでなく、50代、60代になってもゲームを楽しめるような長期的な視点を持つことも大切です。
反射神経が要求されるアクションゲームは将来的に厳しくなるかもしれませんが、戦略系やパズル系のゲームなら年齢を重ねても楽しめるでしょう。
私の60歳オーバーの母も、スマホでパズルゲームをやっています。


また、クラシックゲームの再発売やリマスター版も増えており、若い頃にプレイしたゲームを改めて楽しむという選択肢もあります。
次世代への継承
自分がゲームから得た楽しさや学びを、子どもたちに伝えることも意味のあることです。
ただし、押し付けるのではなく、子どもたちが自然にゲームの楽しさに触れられるような環境を作ることが大切です。
親子で一緒にゲームをプレイする時間は、コミュニケーションの機会としても貴重です。
ゲームを通じて、子どもの成長を見守ったり、一緒に困難を乗り越えたりする経験は、きっと良い思い出になるでしょう。


まとめ:現実と向き合いながらも諦めない


アラフォー世代のゲームライフは、確かに制約が多いものです。
時間は限られ、責任は重く、体力も衰えてきます。
しかし、だからといってゲームを諦める必要はありません。
大切なのは、現実を受け入れた上で、その中でできる最大限の楽しみ方を見つけることです。
量より質を重視し、家族との時間も大切にしながら、工夫次第でゲームとの付き合いは続けられます。
我々アラフォー世代は、ファミコンからプレイステーション、そして現在のNintendo Switch2やPS5まで、ゲーム業界の発展と共に歩んできた世代です。
その経験と知識を活かしながら、これからも上手にゲームと付き合っていきましょう。
仕事も家庭も大切、でもゲームも大切。
そんな贅沢な悩みを持てる我々は、実は恵まれているのかもしれません。
バランスを取りながら、人生を豊かにしてくれるゲームというエンターテインメントを、末永く楽しんでいきたいものです。


時には家族に「まだゲームしてるの?」と言われることもあるでしょう。
でも、胸を張って答えましょう。
「これも立派な趣味なんだ」と!
そして、その趣味が人生をより豊かにしてくれていることを、日々の生活の中で証明していきましょう。
ゲームは逃げ道ではなく、人生を彩る大切な要素の一つ。
そんな風に考えながら、アラフォーゲーマーとしての道を歩んでいきたいと思います。


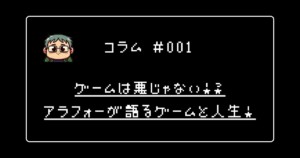
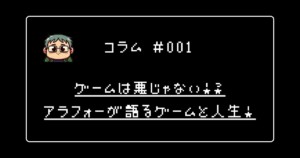
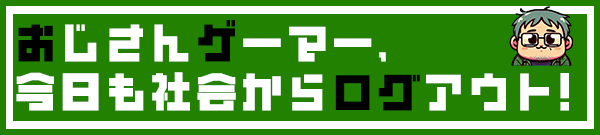

コメント